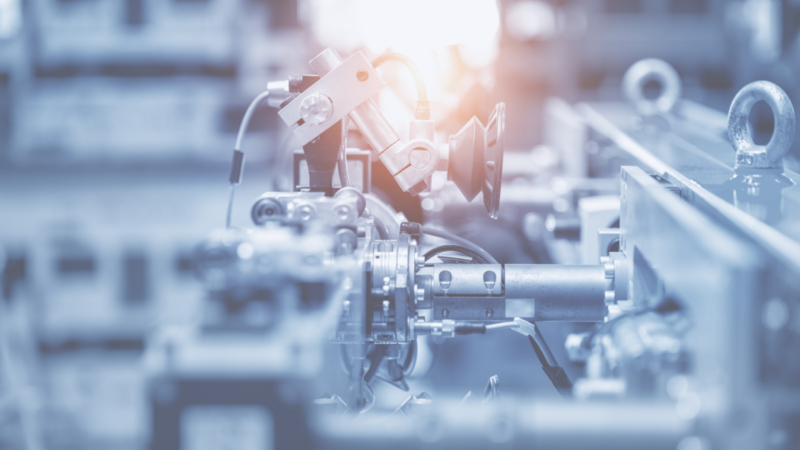コーポレート・トランスフォーメーション(CX)はじめの一歩
とあるプロジェクトのことです。「すべての責任は自分がとる。思い切って進めなさい。」とオーナー社長が言った瞬間、その場にいたメンバー全員が涙を流しました。今思い返すと、この瞬間こそがその会社にとっての本当のコーポレート・トランスフォーメーション(CX)の入り口だったのだと思います。
その会社は非常に長い社歴を有する老舗企業で、同一の商材について①BtoB向け×低価格帯、②BtoC向け×高価格帯、の双方を供給していました。成り行きの事業環境は長らく厳しかったものの、全社一丸となって経営改善に取り組むことで、業績も利益基調といえる水準にまでは回復していました。当面の問題は解決しつつあると思っていたそんな矢先に直面したのが、コロナショックでした。今までの「厳しい」とは比較にならないほどの事業環境の激変は、全力で取り組んできたつもりのこれまでの経営改善を水の泡と思わせてしまう程のマグニチュードでした。
コロナショックを不運なピンチと嘆いて、とりあえず今を耐えるだけの施策をとるのか?開き直りかもしれないものの何とか前向きに受け入れ、最後のチャンスと捉えて更なる改革を行うのか?この会社は、「歴史を紡ぎ続けたい」という切なる想いのもと更なる改革を行うことを選び、生き残りを賭けたCX計画の策定プロジェクトが始動しました。コロナショックで大きな影響を受けたのは②BtoC×高価格帯事業でありましたが、結論的には①BtoB×低価格帯事業から撤退することを決断しました。事業全体の60%強を占めていた①は会社にとっての「祖業」であり、今なお黒字だったにもかかわらずです。
「やめられない祖業」としてよく言われるケースは、往々にして黒字とは程遠く、かつこの会社の祖業ほどの事業規模はないなか、「利益も計上している」「事業規模も全体の半分以上」という状況で祖業からの撤退を取りまとめることは、まさに至難の業でした。祖業に携わるメンバーが全力で抵抗するのはもちろんのこと、他のメンバーも大いに迷い、忖度とも思える行動もありましたが、プロジェクトチームでは事業環境を客観的かつ冷静にひたすら考えることを意識しました。これから10年をとりあえず生きるのではなく、100年後に繋がる戦略とは一体何なのか、相当な葛藤と共に喧々諤々の議論を重ねに重ね、祖業の事業価値がまだあるうちに売却することが合理的にはベスト、という結論に至りました。
ただ、プロジェクトチームとしての結論は、トップの意思決定とイコールではありません。トップが不退転の覚悟で鮮烈な意思決定を行うこと、そしてその実行を担う社員達が腹落ちしなければ、そのCX計画は実行に移らないのです。
いよいよ決断しなければならないある日のプロジェクト会議。まだメンバー全員が腹落ちして当日を迎えることはできていなかったと思います。頭では納得していても心はまだ理解できていない、決断の瞬間を迎えるのが怖くて仕方ない、という人が大半だったのではないでしょうか。そんな中、オーナー社長がプロジェクトメンバーに向けてはっきりと「すべての責任は自分がとる。思い切って進めなさい。」と力強く宣言されました。
「やっぱり何とかなるのではないか」「自分の時に決めたくない」と目の前の苦しさや弱さに負けて、本質的な変容の瞬間にもかかわらず結局意思決定を躊躇してしまう経営者が多いなか、なぜこのオーナー社長は決断ができたのでしょうか。後に社長に聞いてみたところ、「それは自分が創業家だからだよ」とシンプルに一言でお答えいただきました。「創業家としてやめられない」ではなく「創業家だからこそやめるのだ」というこの言葉の裏に、社長を含め創業家ご一族の方々が背負われてきた歴史の重みを垣間見たような気がしました。
そして、CXの瞬間は、社長の発言の直後にもう1回あったと感じています。プロジェクトメンバーの1人であった社長のご子息が、涙とともに「ご先祖様に申し訳ない」とまず発言されたのです。祖業からの撤退という鮮烈な意思決定直後に、合理の下ここまで踏ん張ってきたご子息がその緊張から解放され、感情を露わにした瞬間でした。社長とはまた違う創業家としての想いと覚悟は、その場のメンバー全員に伝播し、溢れる涙と共に全社としての決心を固めるものとなりました。
その後の結果としては、この会社は1人のリストラもない最大限の条件で祖業の売却を成功させ、これからの100年に向けたCXの闘いを今なお続けています。様々な困難を伴う闘いの過程でも、逆戻りせずに前に進むことができているのは、捨象と集中に真っ向から向き合い、逃げずに決断をしたあの瞬間があったからだと言い切れます。
今後もIGPIは、クライアントの皆様と本気の変革を成し遂げるため、合理からも情理からも逃げることなく、「CXはじめの一歩」から共に闘い抜いてまいります。